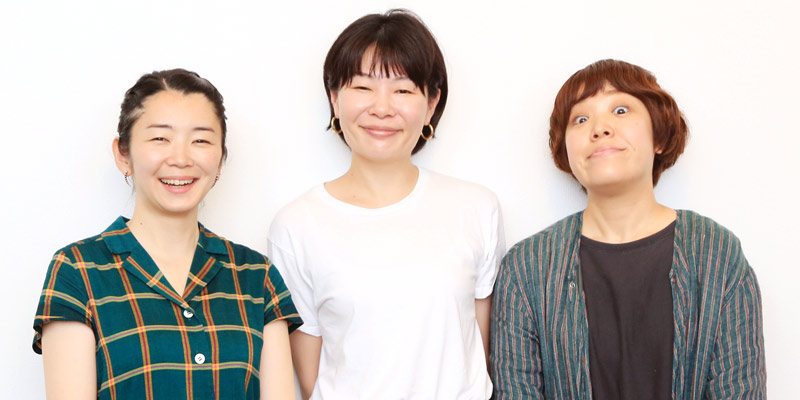――世界は多くの作品で満ちている。それを生み出すあまたのつくり手たち。そのなかで、独自のエネルギーを放つ人たちがいる。なぜつくることをあきらめなかったのか、現場に立ち続けるには何が必要なのか、どうすれば一歩でも次のステージに進むことができるのか。CREATIVE VILLAGEでは、最前線を走るトップクリエイターたちに作品、つくり手としての原点、そしてこれからを問う――
「また“ゆとり”をやりたい!」というキャストたちの熱いエールによって動き始めた、映画「ゆとりですがなにか インターナショナル」。キャストたちを虜にしたのは、宮藤官九郎の秀逸な脚本、そして監督・水田伸生の、作品に関わる人たちの個性と才能を活かす徹底した環境づくりだった。「一番大切なのは準備段階。もうそこで作品づくりのベースは終わっていて、勝負はついているんです」。演出は自分の外にあると気づいたときからが、演出家として本当のスタートなのだと語る。
宮藤官九郎さんは天才です
「ゆとりですがなにか」は、もともと2016年にテレビの連続ドラマとして始まったのですが、テレビというメディアで同じ企画を継続的にというのは無理だったり不自然だったりするんです。それで編成とも話し合った結果、ドラマではなく映画化を目指そうということになりました。それで18年にまず宮藤官九郎さんに相談しました。ドラマ「ゆとりですがなにか」は、脚本家の宮藤さんが「ゆとり世代を題材に書きたい」とおっしゃったことから始まった作品で、企画発案者である宮藤さんは最重要人物ですから。宮藤さんとしては、お客様が劇場にまでわざわざ観に行こうという動機づけとなるような題材を物語に盛り込めるのかなど、いろいろ躊躇があったようですが、おかげさまで、キャストのみなさんのやりたいという気持ちとスタッフの熱が通じて、「やってみようかな」という気持ちになっていただけた。そこからはトントン拍子で進みました。

19年には脚本も完成し、翌20年10月からに撮影する予定でキャストのスケジュールを全部押さえさせていただいていたのですが、コロナ禍で延期することになり、次は2年後にしかみなさんのスケジュールが取れなくて。そのうちにLGBTQやハラスメントといった社会問題や、リモートワークといった働き方や暮らしの変化といったことが気になり出し、改めて脚本を書き直しての撮影となりました。脚本家・宮藤官九郎は天才です。「ゆとりですがなにか」もそうですが、時代を掴むといった面がますます際立ってきましたよね。宮藤さんは宮城県出身で、東日本大震災があって、「あまちゃん」(NHK/13)のような作品が生まれたし、「ゆとりですがなにか」も、宮藤さんのなかで書くものが、自分の内にある物語から外に向いていくタイミングだったような気がします。脚本家にはそういうふうに変化していく人がいるんです。ずっと同じことを書くタイプの人もいますが、宮藤さんや坂元裕二さんは変化していて、家族ができたり、お子さんの成長に合わせて書くものも変わってきている。そういうところにすごくシンパシーを感じています。

演出とは、キャストやスタッフのお手伝いをすることなんです
僕自身も立てる企画は時を経て変化していますし、演出面でも、若い頃は、言ってしまえば、演出家気取りでした。ものの見方や考え方が、“個人 対 社会”なんです。でも家庭や子供を持ったり、あるいは親が年老いて介護の必要が出てきたりとか、僕自身のいろんなことが変化していきますよね。そうすると“家庭 対 社会”といった感じに意識の質が変わってきて、社会に対する目つきも対応も変化する。演出が変わるというのは手法などではなく、考え方どころじゃない、自身の哲学が変わることなんです。で、個人で肩肘張って演出家を気取っていたことの愚かさに気づく。自分の中にあるものを人に伝えたがったり押し付けたり、世の中を巻き込みたいとか、自分の中に演出があると思っている限りは、演出家気取りに過ぎない。そう思ったのは、30代後半から40歳にかけて、仕事はノリノリのときです。ノリノリなんだけど、ある日突然、雷に打たれたように気づいたんです。

僕の外に演出はある———演出する上でずっと心がけているのはその点です。演出とは、キャストやスタッフのお手伝いをすることなんです。どうすれば彼らが個性や能力をいかんなく発揮できるか、どのようにしてバラバラの個性と能力を持っている人たちをひとつの方向に向かって動かせるか。ホン(脚本)づくりもそうだし、スタッフ集めも、キャスティングもそうです。プロデューサーの手助けを借りて、キャストとスタッフを活かすための環境をつくることが一番大切な準備です。それが85%。そこに、あの優秀なキャストのみなさんがやってくるわけです。そうすると、周到な準備に安心感を覚えて「この現場は大丈夫」だと思ってもらえ、信頼して集めたメンツですから、放っておいても良いパフォーマンスをしてくれる。あとは、ちょっとだけ油をかけたり、鎮火させたりするぐらいで(笑)。現場でできることなんてなくて、やったとしても2%ぐらいです。そうじゃないとうまくいっている現場とは言えないと思います。あとはポスプロが13%。これは大切ですから、それぐらいのパーセントはあるんです。

人より1本でも多く観る。それを自分に課す
どんなスタッフと仕事をしたいか。それは、僕とやりたいと思う気持ちがある人ってことがまず第一です。逆も然りで、例えば、もう何年も一緒にやってくれているカメラマンの中山光一<映画「なくもんか」(09)、ドラマ「MOTHER」(10)ほか>には、最初にメールを出し、返事を待ち、電話をし、留守電に吹き込み、まったく応答がないから現場に行って様子を観察し、違う日に再び訪ねてお手すきのときに話しかけ……そこまでするとさすがに向こうも僕に興味をもってくれるようになる。仕事は、与えた・与えられたみたいな関係では決してうまくいかないと思います。経験が浅いからダメだってことはなくて、やる気があることが第一で、その先に能力のある人が生き残っていく。でも能力は身につけることができますから。

映像制作を仕事とするなら、まず心がけるのは、「人より1本でも多く観る」ということ、それを自分に課すことです。そして自分以外の人間が関わった作品を観るときは、やっぱり良いところを探すべきだと思います。否定することはとても簡単なのだけど、相手を尊重しない限り学ぶことはできないし、リスペクトがないものからは何も得られない。つまり、自分にインプットしようという気持ちがとても大切で、インプットがない人は当然アウトプットできないわけです。10インプットがあったとしてもアウトプットできるのは1か2ぐらいですから。とにかくたくさんインプットすることが大事です。僕は年間100本以上演劇を観るし、100本以上映画も観ます。今日も朝の8時から映画を観てきました。劇場じゃなくても、幸いなことにいまは配信でも観ることができるし、そういうものを活用して古いものから新しいものまで、片っ端から観るといったぐらいの気持ちを持ったほうがいい。そして興味がある作品がれば、お金を貯めて映画館で観る。配信は視聴だから視覚と聴覚以外は使ってなくて、あとの感覚は劇場でしか体験できない。劇場で体験する映画と、配信で観る映画はやっぱり違いますから。

「演劇を学べ」。担任の一言で、日本大学芸術学部に進む
僕は広島市で生まれ育ちました。高校時代に演劇に関わったことがこの世界に入るきっかけなのですが、正確にいうと、僕と演劇との出会いは母親。母親が芝居好きだったんです。そして映画は父親です。父親は、戦後シベリア、中国に抑留されていたので、昭和30(1955)年まで帰ってこられなかったのですが、僕が昭和33(1958)年に生まれてもの心ついてから父親が病に伏せるまで、毎週日曜日の午前中は必ず映画を一緒に観に行っていました。戦前、広島は軍都として賑わっていて映画館も劇場もたくさんあったので、広島の人にとっては映画や芝居というのはとても身近なものでした。だから父親にとっては映画を観ることが日常だったし、自分の失った青春を取り戻す時間でもあったのだと思います。幼い頃の僕は重い小児ぜんそくを患っていて、体育もできない、旅行にも行けない体でした。やれたことといったら読書ぐらいで、子供向けの文学書から父親や祖父の蔵書まで、ものすごい量の本を読んでいました。夏休みには読むものがなくなって当時流行りの百科事典を繰り返し見たり。いまそれに助けられています。大雑学王ですから(笑)。それが小学校4年生のときに心臓弁膜症で半年間入院して体質が変わりぜんそくがおさまった。スポーツをやるようになったのはそれからです。

バレーボールをやるために進学した高校がたまたま高校演劇の名門校で、有名な顧問の伊藤隆弘先生という方がいらして、僕の3年生のときの担任でもありました。バレー部は3年生の夏の大会で負けて引退することになるのですが、とても厳しい部活で丸刈りだったんです。伊藤先生は戦争や被爆を題材に戯曲を書かれていたので、丸刈りで痩せていてバレー部でずっと体育館にいたから色白の僕を見て、「こんないい復員兵キャストはいない」と(笑)。そうやって縁もゆかりもないと思っていた演劇部の応援に行くようになり、大学進学を前に進路で迷っていたら、伊藤先生が「演劇を学べ」と。それで日本大学芸術学部演劇学科に進みました。大学の専攻は演出で、なかでも舞台制作に興味があって、俳優教育を仕事にしたいと思っていました。でも母親に泣かれて。本当に穏やかな人で、「就職試験を人並みに受けて、その結果でまた話し合いましょう」と静かに諭されました。それで少しでも芝居のそばにいられる可能性のあるところを考え、ドラマをつくっているテレビ局と、CMをつくっている広告代理店を受け、日本テレビと博報堂が採ってくれました。

インプットがない人は終わってしまうと身に染みて思いました
大学の先生の勧めもあって日本テレビに入社し、運よくドラマの現場に就けて、最初の現場が「池中玄太80キロ Ⅱ」(81)でした。俳優業だけをやっている専門職の人が集まってつくっていた、あの時代のドラマほど幸せな現場はなかったと思います。制作部というポジションもまだなく、僕たち演出部がロケハンもお弁当の手配などもすべてやっていましたし、すごく学びが多かった。ただ僕は、全員が尊敬できる演出家ではないと思っていました。この人はすごいけど、この人は大したことないなとか、生意気に思ってしまうような人間だったから、イヤな後輩だったと思います。すごいなと思う演出家は、知らず知らずのうちにその人のペースに乗せられてしまっているような人。田中知巳さん(「前略おふくろ様」「熱中時代」ほか)、石橋冠さん(「池中玄太80キロ」ほか)、吉野洋さん(「星の金貨」ほか)といった、決して何かを強要しているわけではないのに、いつの間にか周りがその人のペースにすっかりハマってしまっているという。「そうか、こういう人が演出家なんだ」と思いました。それで演出をする優れた先輩たちに興味を持つようになり、鴨下信一さん演出のドラマ「ふぞろいの林檎たち」に出演していた石原真理子さんに頼んで、彼女の運転手のふりをしてTBSさんの稽古場に忍び込み(笑)、鴨下さんの演出ってこうなのかとか、プロデューサーの大山勝美さんってこういうふうに話すのかとか、1日中観察していました。逆に僕たちが生田スタジオで撮影していると久世光彦さんがお見えになったり、NHKの和田勉さんが現れたり、当時は演出家同士の交流もあったし、面白い時代でした。

それが、入社3年目に突然、バラエティー班に異動することになるんです。それは編成上の都合で、ドラマ枠が土曜日21時の1枠という時代が到来、そうすると僕は余剰人員になるわけです。それで「水田は俺がもらうわ」と手を挙げてくれたのがプロデューサーの細野邦彦さんだった。細野さんは、「コント55号の裏番組をぶっとばせ!」や「テレビ三面記事 ウィークエンダー」などを手がけていた敏腕プロデューサーで、それから「TVジョッキー」や「ルックルックこんにちは」といった細野班の番組をやるようになりました。僕にとって何より大きかったのは、そこで芸人さんたちと一緒に仕事をするようになり、彼らの努力する姿に触れられたことです。北野武さんや片岡鶴太郎さん、明石家さんまさんもそうですが、実はすごく努力家なんです。あの武さんですら楽屋で横になっている瞬間がなかった。時には中学生の教科書を読んでいたり、ある時は紙の鍵盤でピアノの練習をしていたり、ある日はタップダンスを踏んでいたり、とにかくずっと勉強している。あれほどのトッププレーヤーがこんなに努力しているのだから、僕みたいな人間が勉強しなくなったらダメだ、インプットがない人は終わってしまうと身に染みて思いました。本当のトップクラスの芸人さんたちのものすごい努力を知ることができたのは、僕にとって本当にデカかった。

ずっと企画者であろうとしている
企画を考え続けるということは、いまにいたるまでずっと続けていることですし、そうあるべきだと僕は考えています。だからこそ、作品づくりにおいて、何かを進めなければならないときは、やはり企画者の意思が尊重されるべきだと思います。そういう意味でも制作者として現場で発信を続けたいのなら、企画を考え続けることが必要なんです。それはみずからに課してでもやらなければならないし、そこにおいてもやっぱり僕には、楽屋での武さんやさんまさんの姿が大きな糧になっている。僕はドラマも映画もどちらも好きだし、どちらもやり続けたい。ただ、仕事というのはオーダーがあってのもので、どちらを求められるかで決まっていくわけです。で、オーダーされ続けるために、繰り返しになりますが、僕はずっと企画者であろうとしています。だからこそ、演出家、監督として人様のアンテナに引っかかることができているのではないかと思っているんです。

ドラマとして始まり、このたび映画となった「ゆとりですがなにか」は、僕にとって、紛れもなく相当に深い愛着がある作品です。岡田将生くん、松坂桃李くん、柳楽優弥くんをはじめ、仲野太賀くんや安藤サクラさんも、ほとんどのレギュラーキャストは僕みずから動いてキャスティングしました。それは、プロデューサーより圧倒的にキャリアが長い僕が動いたほうが、決着が早いと思ったからなのですが、結果、無理だと思っていた第1希望のキャスト全員の出演がかなってしまった。宮藤官九郎さんという大きな才能と宮藤さんと一緒にそれまでつくってきた作品が大きく背景にあったからこそだと思うのですが、こんなこというとおこがましいけれど、宮藤さんに対する誇らしい気持ちと、僕らスタッフも自分たちのキャリアに対して、じんわり自信がついた出来事でした。と同時に、とてつもない責任感が湧き上がってきました。映画「舞妓Haaaan‼︎!」(07)を書くときに一度も京都に行かなかった宮藤さんが、ものすごい数の“ゆとり世代”に会って取材しているわけです。宮藤さんの本気もすごかったですから。そうやって、宮藤さん、キャスト、スタッフが心をひとつにしてここまでやってきた作品です。だから、もっとやりたいんですよね。続編、やりたいんですよ。

1958年広島県生まれ。日本大学芸術学部演劇学科卒業後、81年日本テレビ入社。数々のドラマの演出、プロデュースを手がける。2006年に映画「花田少年史 幽霊と秘密のトンネル」で映画監督デビュー。ドラマ「Mother」(10)で第37回放送文化基金賞テレビドラマ番組賞ほか、ドラマ「Woman」(14)で芸術選奨文部科学大臣賞放送部門受賞。舞台演出、また俳優の教育育成のワークショップで講師も務める。主な作品に、テレビドラマ「恋も2度目なら」(95)、「恋のバカンス」(97)、「Dr.倫太郎」(15)、「anone」(18)、「獣になれない私たち」(18)、「初恋の悪魔」(22)、映画「舞妓Haaaan!!!」(07)、「252 生存者あり」(08)、「なくもんか」(09)、「謝罪の王様」(13)、「アイ・アム まきもと」(22)、「おまえの罪を自白しろ」(23)ほか。大反響を巻き起こした、ドラマ「ゆとりですがなにか」(16)は宮藤官九郎の芸術選奨文部科学大臣賞放送部門をはじめ多くの賞を受賞、スペシャルドラマ「ゆとりですがなにか 純米吟醸純情編」(17)、スピンオフドラマ「山岸ですがなにか」(Hulu/17)を経て待望の映画化が実現した。
野心がない、競争意識がない、協調性がないと揶揄される「ゆとり世代」も30代半ばを迎え人生の帰路に立たされていた。妻の茜(安藤サクラ)との仲はギクシャク、家業の老舗酒蔵も危機に見舞われる坂間正和(岡田将生)、外国人転校生がやってきてクラス運営に悪戦苦闘するいまだ女性経験ゼロの小学校教師・山路一豊(松坂桃李)、事業に失敗し中国から舞い戻ってきたフリーターの道上まりぶ(柳楽優弥)。≪Z世代≫≪働き方改革≫≪テレワーク≫≪多様性≫≪グローバル化≫……新時代の波に翻弄されながら、ゆとり3人組のドタバタ人間ドラマ劇が幕を開ける。



出演:岡田将生、松坂桃李、柳楽優弥、安藤サクラ、仲野太賀、吉岡里帆、島崎遥香、中田喜子、吉田鋼太郎
脚本:宮藤官九郎、音楽:平野義久
エグゼクティブプロデューサー:飯沼伸之、田中宏史、プロデューサー:藤村直人、仲野尚之、ラインプロデューサー:宿崎恵造、監督補:相沢 淳、撮影:中山光一(J.S.C.)、照明:市川徳充、録音:鶴巻 仁、美術:内田哲也、VFXスーパーバイザー:オダイッセイ、編集:和田 剛、スクリプター:阿保知香子、制作担当:近藤 博
Ⓒ2023「ゆとりですがなにか」製作委員会
10月13日(金)より全国公開
インタビュー・テキスト:永瀬由佳