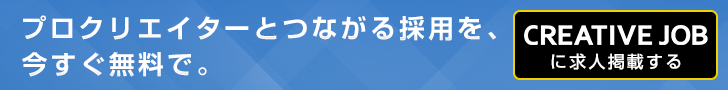さまざまな人気作を世に送り出してきたドラマ&映画プロデューサー・山内章弘さん(東宝株式会社)。『トリック』シリーズにはじまり、『電車男』『チーム・バチスタの栄光』『モテキ』『進撃の巨人』『アイアムアヒーロー』『シン・ゴジラ』『怒り』『君の膵臓をたべたい』『検察側の罪人』、最近では『アルキメデスの大戦』など、関わったタイトルをあげればきりがありません。
東宝株式会社映画企画部部長。
1992年に東宝株式会社に入社後、テレビドラマ制作の部門に所属。テレビドラマを中心に番組制作を行う中で『トリック』シリーズがヒットし、映画化。近年では『シン・ゴジラ』『屍人荘の殺人』など数々の映画でエグゼクティブ・プロデューサーを務めている。
山内さんは今、新たな才能を発掘する企画「GEMSTONEクリエイターズオーディション」の審査員をつとめています。その山内さんに、これからの映画業界や、次世代のクリエイターについてお伺いしました。
「GEMSTONEクリエイターズオーディション」とは
東宝株式会社とAlphaBoat合同会社が共同運営し、YouTube及びSNSを活用したオーディションプロジェクトは、2018年11月にはじまりました。第五回を迎える今回のテーマは「ショートホラーフィルムチャレンジ」として、6月15日(月)の〆切(※)までに、ホラー短編映像を募集しています。
※ この度の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、応募締切が延長されました。詳細はこちらをご覧ください。

誰もが映像作品をつくれる時代における「プロ」とは
──山内さんはこれまでさまざまな映画を手がけてこられました。プロデューサーとして、作品のどんなところに注目し、大事にされていますか?
山内 「心が揺り動かされるかどうか」ですね。一作のなかに何度も心が動くポイントがあるものもあれば、イマイチだなと思って見ていると最後にものすごいハードパンチがくる映画もあります。どんなアプローチでも構わないけれど、とにかく「心が動く」総量が多ければ多い方がいいですね。
──心が揺り動かされる仕掛けのつくりかたは?
山内 「どれだけ人に伝えたいと思っているか」が大切。未熟だけれど何故か心に響く映画もあるし、作り手の経験がモノを言う映画もあります。その根底にあるのは「伝えたい」という熱だと思うんですよ。
──技術面ではいかがですか? 映像の表現方法はどんどん変化していると思いますが。
山内 CG技術が映画の作り方を根幹から変えてしまった。かつては表現できないと思われていたストーリーが実現可能になったことは本当に大きな変化だと思います。
加えて、撮影機材の革新によって、撮影現場も大きく変化しました。フィルム撮影と違って長時間の撮影が可能になり、後処理できるゾーンが広がったことによって全てを現場でやり切る必要が無くなりました。
それにはもちろん功罪あるけれども「撮影」行為に対する現場の考え方はだいぶ変わってきたと思います。
──技術革新がどんどん起きているなか、映像作家に必要なものは?
山内 「表現したいものがきちんとあるかどうか」に尽きると思います。今は誰でもスマホである程度のクオリティのものが撮影でき、子どもでも使えるような編集ソフトで多くの人が観られるレベルのものが簡単にできてしまう。
そういう中では、結局何を表現し、何を伝えたいかをクリエイターがきちんと持っているかどうかが一番大事です。表面的な表現だけを追いかけているものは、多くの人の心を揺らすものにはならないんじゃないかと思います。
──誰でも作品がつくれる時代において、プロのクリエイターはなにが違うのでしょう?
山内 「やり続けられる」ことだと思います。一本うまくいかないと、考えすぎて次がつくれなくなる方は多いんです。「オレは100点出せるはずだ、出さないと世に問えない」と思いすぎちゃうと続かない。
プロだから50点ではダメだけど、どんな環境でもコンスタントに70点以上を出し続けられ、時には120点を叩き出せる、そんな人がプロなんだと思います。
──とくに映画づくりにおいては、パートナーも大事なのでは?
山内 そうですね。良いパートナーを見つけることはクリエイターにとって大事な条件だと思います。
映画では監督が率いるチームを「○○組」などと言ったりしますが、一緒に経験を積んでいくことで信頼をおけるスタッフ達とチームになっていければ、それこそが「組」になる。監督とプロデューサーというのも、監督のフィルモグラフィーにおける次のステップや、今の世の中にどういうものが響くのかなどを語り合って具現化していけるパートナーとして、とても重要な関係。
また、プロデューサーにとっては、良い脚本家と良好なコミュニケーションが取れるかどうか、というのも重要です。アメリカではプロデューサーと脚本家が一緒になった「ショーランナー」というシステムがありますが、それぞれの得意技を持っている脚本家と能力のあるプロデューサーが仕事をする方が、面白い作品が数多く生まれることになる。プロデューサーの企画をきちんと言語化できる脚本家とタッグを組めることは大きな要素です。
もちろん相性もある。だから、場数を踏んで、なるべくいろんな人と出会って、うまくいかなければ深刻にならずに「自分と合わなかっただけだ」と次の現場に挑んでいく。そうして、自分の目指すビジョンと近いパートナーを早く見つけて欲しいと思います。
どう面白くできるか、を考えるのがクリエイター

──山内さんご自身は映画をつくりたかったのでしょうか?
山内 もちろん映画会社に入った以上は映画の制作がしたかったのですが、私が入社した約25年前は、東宝で制作している映画は『ゴジラ』シリーズと時代劇それぞれ年に一本くらいしかなかった。邦画界は斜陽産業の最たるものでした。
これではなかなか若手が経験を積める機会はないなと考え、作品数の多かったテレビドラマの部署を志望し、幸いにも取ってもらえた。それから10数年、テレビドラマを中心にバラエティ番組などの企画制作をする中で、ドラマ『トリック』などが生まれ、テレビ部にいながら『トリック』の劇場版をつくったりしました。
当時はテレビドラマDVD化のはしりで、視聴率は低くてもDVDがものすごくヒットしたのでパート2が決まる、という幸せなことが起きた作品でした。『トリック』は、何度でも繰り返し見たいと思うコアな方々に支持してもらえ、14年も続いて本当に作り手冥利に尽きる作品になりました。
その頃はドラマ制作に面白味を感じていたので、映画の部署に異動したいという気持ちはなくなっていました。制作会社にとってテレビドラマは受注産業なので、企画をテレビ局さんに売り込んでそれが通らないと制作が出来ないというハードルが高い仕事。当時企画が次々通っていて、ちょっと調子に乗っていたんですね(笑)
──今は映画調整部(編成部門)を経て、映画企画部長をつとめられています。これから映像製作に携わるうえでの面白さはどんなところに感じていますか?
山内 映像の配信システムが出てきたことで、より広く深く作品が楽しまれるようになってきました。『エヴァンゲリオン』や『シン・ゴジラ』もそうですが、読み解き型の作品が増えてくる気がします。一回観ただけではわからない要素や、何回か見て「なるほどそうだったか」と気づく作品や、回答はないのに「これはきっとこういう意味だ」と盛り上がるような見方が主流になるかもしれない。そうすると、今までは考えられなような仕掛けやストーリーテリングが出来るようになるではないか。それは作り手として面白みを感じます。
──どんな作品が主流になるかを読むのは、プロデュース的な視点かと思います。作家自身もそのような目線を意識している方がよいですか?
山内 そういう目線を持つクリエイターも増えてきている気がするけど、それはむしろプロデューサーの仕事。
それよりも、日々アップデートされる機材を面白く使う方法を考えつけたりするのがクリエイターの仕事じゃないですかね。
機材の開発者は「こんなに良いものができましたよ!」というところまでで、それをどう使えばいいかまでは考えない。クリエイターは、その機材の仕組みや原理はわかってなくてもいいので、「これとこれを組み合わせたらこんなに面白いことができるんじゃないか」「こんな機材があるならこんなこともできるよね!」と考えるのが仕事。
テレビだって、番組をつくっている人達はどのような仕組みで映像が映っているかまで詳細に理解できているわけではないですからね。
これから考えもつかなかった機材やソフトはどんどん出てくるでしょう。映像を作る環境は明らかに良くなっていく。それを使って若い人達が新しい発想で「これとこれを結びつけてみよう」と取り組んでくれたら、僕らなんかには思いもつかないようなアイデアが出てくるんじゃないかと期待しています。
新しい才能の原石を磨くチャンスとなる企画を
──次回の応募テーマは「ホラー」ですね。
山内 GEMSTONEは、社内の様々な部署の若手スタッフ中心に進めている、社内横断プロジェクトです。映像部門の担当者もいれば、演劇部や、管理部門の人もいます。
第一回目は、「東宝にとって一番大事な存在をみなさんに遊んでいただこう」ということで、『ゴジラ』をテーマに開催しました。その後、クリエイターを目指す人達が興味をそそられる題材はなんだろうと試行錯誤して、第二回はキャラクター制作、第三回は小説のプロモーションビデオ、第四回は短編アニメーションを募集するなど、多種多様な展開をしてきています。
五回目となる今回は、「ジャンルを絞れば発想しやすいし、ホラーは若手登竜門の題材」と演劇部3年目の若手から案が出たものです。募集も10秒以上5分以内と幅広いので気楽にもできるし、本気で怖いものや新しいものをつくることもできる。テーマとして面白いと皆で話し合い、決定しました。
──応募することのメリットや可能性は?
山内 これまでに受賞された方々とは様々な企画を進めています。短編映画の企画をはじめたり、東宝のYouTubeチャンネルで作品を展開したり、新しいキャラクターの商品化を目指したり。
また、新規事業の提案をもらって一緒に事業化しようとしていたりと、それぞれのクリエイターに合った企画が進行しています。なかには、選考外となってしまった方にアプローチさせていただいたケースもあります。すぐに世に出ていく人もいれば、何年もかけて一緒に頑張っていきましょうという人もいる。
ただ、予想以上に成果は出てきていると思います。若いクリエイターの方が多いので、東宝の若い社員と一緒に企画をすすめることでの化学反応が起きているのも魅力。才能から出発していろんなことが展開していく、まさに「原石」で、この企画が出発点になっているのではないでしょうか。
ですから、応募作を見ているのはもちろんですが、我々はクリエイターの方々の「発想」や「可能性」そのものを見ているのだと思ってください。
ホラーの概念を破壊する作品に出会いたい

──今回はテーマが「ホラー」です。このジャンルにおいてはどういったクリエイターに出会いたいですか?
山内 僕がホラー映画を作れば、当然経験値である程度までの作品は利き腕で出来るでしょう。でも若手の方から出てくる発想は僕らには及びもつかないんじゃないかという期待がある。だから今回は僕らの想像を軽々と超えて欲しい。これまでのホラーの発想そのものを破壊するようなものが出てくると嬉しいですね。
──これまでの「ホラー」を破壊する、とは?
山内 ホラーといえば、80年あたりにアメリカで流行ったジェイソンやブギーマンのように、はっきりと恐怖の対象があって、それに怯える人達の物語を思い描くことが多かった。殺人鬼が出てきて、逃げ惑う人がいて……という暴力や凶暴性への恐怖。逆に日本では、『番長更屋敷』のような怪談や『リング』などのJホラーに代表される因習や怨念に纏わる恐怖がメイン。それらは今でもいわゆる「ホラー」に対する人々の印象として根強く残っています。
ただ、昨今だんだんと恐怖という概念自体が変わってきているように思います。今は、刃物を持った人に追いかけられる怖さや、ヒュードロドロの怖さよりも、ネットで匿名の人や不特定多数の目にさらされる方が恐ろしいと、恐怖の対象が変わってきているのではないか。しかもネット社会によって価値観が混ざり合い、恐怖の感覚が世界共通になりつつあるような気もしています。
そんな中、最近のホラー映画の流行は、今までの文脈とは違ってきている。たとえばジョーダン・ピール監督の『アス』やアリ・アスター監督の『ミッドサマー』は、もはやホラー作品なのかもわからない。それでも人間の根源的な恐怖や闇みたいなものを映像に落とし込んでいて、数年前には考えられなかった新しい表現の仕方だと思います。そういった「なるほどこういう手があったか!」という作品が出てきたらすごく嬉しいです。
──これまでの概念を取っ払うような作品への期待ですね。
山内 映画の面白味って、2時間の中で考え方が180度変わっちゃったりすることがあることだと思う。心が揺さぶられ、感情が忙しく揺れ動く。感動、涙、恋愛なんかがわかりやすい例だけど、「恐怖」というのも大きく心揺れる要素の代表例です。今回のGEMSTONE企画から、ホラーの新しい表現方法がうまれてきてほしい。そういう才能と出会いたいですね。
インタビュー・テキスト:河野 桃子/企画・撮影:ヒロヤス・カイ/編集:CREATIVE VILLAGE編集部