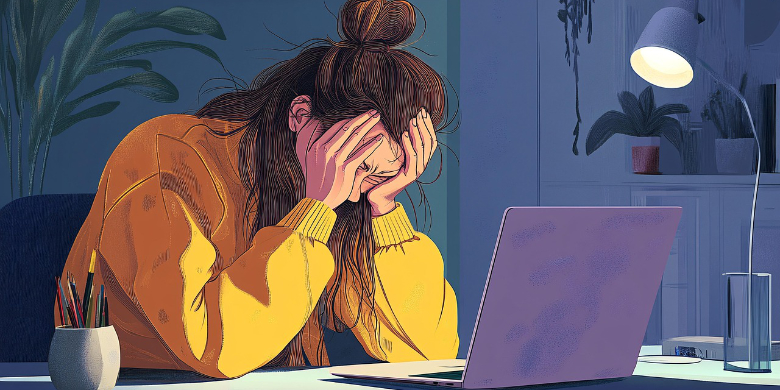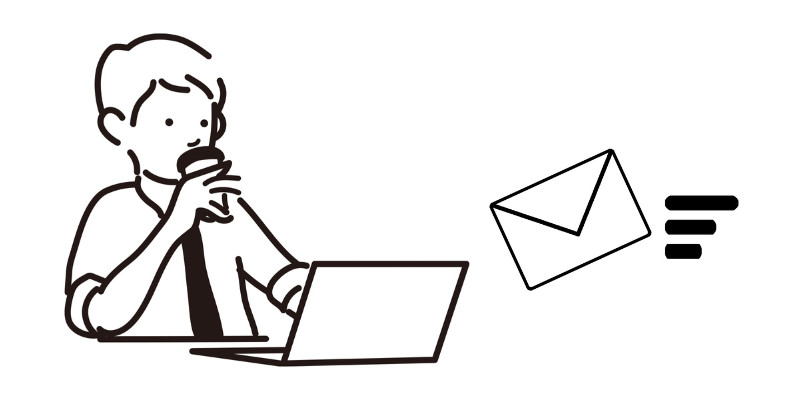かつては紙媒体中心だったデザインの世界も、今やWebサイトをはじめとするデジタル領域へと大きくシフトしています。企業や個人がオウンドメディアを運営するのが当たり前となった現代において、Webサイト制作の需要は依然として高いように見えるかもしれません。
しかし実際には、「Webデザイナーの仕事はなくなるのでは?」という声も少なくありません。理由は、AIやノーコードツールの進化、フリーランスを含めたWebデザイナー人口の急増、そして求められるスキルの高度化など、多岐にわたります。
インターネットを取り巻く環境が急速に変化する今、Webデザイナーに求められる役割も大きく変わりつつあります。本記事では、「Webデザイナーは本当になくなるのか?」という疑問に向き合い、現状の業界動向や今後も活躍できる人材の条件について、わかりやすく解説していきます。
Webデザイナーの仕事は本当になくなるのか?
「Webデザイナーの仕事は将来的になくなるのでは?」という不安の声を、最近よく耳にするようになりました。特にSNSやブログ、動画サイトなどで「AIに仕事を奪われる職種ランキング」などが取り上げられるたびに、不安を感じるWebデザイナーも多いのではないでしょうか。
しかし、結論から言えば、Webデザイナーの仕事が“完全になくなる”可能性は低いと考えられます。ただし、今までと同じ感覚で仕事を続けていれば将来的に仕事が減っていく可能性があることも事実です。では、なぜ「Webデザイナーはなくなる」と言われるようになったのでしょうか?
「なくなる」と言われる背景
「Webデザイナー なくなる」という言説の背景には、いくつかの大きな変化があります。
まず1つ目は、ノーコードツールやAIの進化です。Wix、STUDIO、Webflow、さらにはCanvaなど、専門知識がなくても美しいWebサイトやデザインを制作できるツールが急速に普及しています。これにより、従来Webデザイナーが担っていた作業の一部が一般ユーザーでも可能になりつつあります。
2つ目は、Webデザイナー人口の急増による競争の激化です。フリーランスの増加や未経験からの転職者の参入により、比較的参入しやすい職種として注目される一方、案件の単価下落や差別化の難しさが問題視されるようになっています。
そして3つ目が、企業側のニーズの変化です。「見た目の良さ」だけではなく、ユーザー体験(UX)や成果(CVR)を重視する企業が増えており、従来のビジュアル中心のスキルだけでは対応しきれない場面も増えています。
このような背景から、「Webデザイナーは将来的に不要になるのでは?」という声が出ているのです。
現状の需要と将来性
とはいえ、Webデザイナーの仕事がまったくなくなるわけではありません。むしろ、スキルの幅を広げたWebデザイナーは、今後さらに求められる存在となっていくでしょう。
たとえば、以下のような領域ではWebデザイナーの需要が根強くあります。
- UX/UI設計が求められるアプリやWebサービスのデザイン
- ECサイトやLP(ランディングページ)の最適化
- ブランディングに直結するコーポレートサイトの構築
- マーケティング施策と連携したデザイン制作
また、ビジネス寄りの視点やマーケティング理解を持った「ハイブリッド型Webデザイナー」へのニーズはむしろ増加傾向にあります。
要するに、今後もWebデザインのニーズは確実に存在しますが、「従来のままのWebデザイナー像」ではなく、「変化に対応できるWebデザイナー」が生き残っていく時代に入ったと言えるのです。
Webデザイナーの仕事がなくなると言われる理由

「Webデザイナーは将来的に不要になる」といった声の背景には、業界や社会構造の変化が複数絡み合っています。ここでは、その具体的な要因を4つの視点から解説していきます。
Webデザイナー人口の増加による競争激化
ここ数年でWebデザインを学ぶ環境が整い、未経験からの転職や副業としてWebデザイナーを目指す人が増加しています。オンラインスクールやYouTube、SNSを通じて独学でスキルを身につけることも可能になったため、比較的参入障壁の低い職種として注目されているのです。
その一方で、案件数の増加が人材の増加に追いつかず、単価の下落や案件の奪い合いといった状況も生まれています。特にクラウドソーシング系のプラットフォームでは、低価格競争が加速しており、「スキルはあるのに仕事が取れない」と感じる人も少なくありません。
こうした現状が、「Webデザイナーは飽和状態」「このままでは仕事がなくなる」といった不安につながっています。
AIやノーコードツールの進化による自動化
もう一つの大きな要因が、AIやノーコードツールの進化です。ChatGPTのようなAIツールは、コードの自動生成やデザイン案の提案まで行えるようになり、FigmaやFramerのようなデザインツールもAIとの連携機能を搭載するなど、効率化が急速に進んでいます。
また、STUDIO、Webflow、Wix、Canvaといったノーコード・ローコードツールの台頭により、非エンジニアや非デザイナーでもある程度のWeb制作が可能になっています。
これらのツールはまだ完全に人間の代替とは言えないものの、「単純なデザイン作業はAIやツールで済む」という流れが確実に進行中です。このため、特に「テンプレートに近いWeb制作」を専門にしていたWebデザイナーは、今後の立場が厳しくなる可能性があります。
SNSやプラットフォームの普及によるWebサイトの必要性の変化
かつては「ビジネスをするならWebサイトが必須」という時代がありました。しかし現在では、InstagramやTikTok、X(旧Twitter)などのSNSやYouTubeチャンネルを中心とした情報発信・集客が主流となりつつあります。
さらに、BASEやShopify、note、Peatixなどのプラットフォームを使えば、自社サイトを持たなくても販売・集客・イベント開催が可能です。こうした背景から、「そもそもWebサイトを作らなくてもビジネスが成立する」ケースが増えてきました。
これはつまり、「Webデザイナーに依頼する必要がない」場面が増えているということでもあります。もちろん、ブランド戦略や本格的なWebマーケティングを行う企業ではサイトが必要ですが、小規模事業者や個人にとっては外注コストを削減する選択肢が増えたことが、業界への影響を及ぼしています。
企業の予算削減による外注の減少
不景気や物価高騰の影響を受けて、企業のコスト削減志向は年々強まっています。その中で、Web制作にかける予算が削られるケースも少なくありません。
たとえば、以前は外注していたWebサイトの更新作業やページ追加などを、社内でノーコードツールを使って内製化する動きが増えています。また、制作自体を一括して依頼するのではなく、テンプレートやパーツの流用によってコストを最小限に抑えようとする企業も多いです。
こうしたコスト圧力がWebデザイナーの案件数や単価に影響し、「以前より仕事が取りにくくなった」と感じる原因となっています。
今後も求められるWebデザイナーの特徴

「Webデザイナーの仕事はなくなる」と言われる時代においても、企業やクライアントから継続的に求められる人材には共通した特徴があります。単なるビジュアル制作にとどまらず、本質的な価値を提供できるWebデザイナーこそが、今後も生き残り、選ばれ続ける存在となるでしょう。
以下では、時代の変化に対応しながらも求められるWebデザイナーの具体的な資質やスキルについて解説します。
UI/UX設計のスキル
現在、Webデザインにおいて「見た目が美しい」だけでは通用しなくなっています。ユーザーが迷わず行動できる導線設計、目的を達成しやすい情報配置など、ユーザー体験(UX)と操作性(UI)に基づいた設計力が、あらゆるWebサービスで求められるようになってきました。
特にECサイトやアプリ、BtoBサービスなどでは、「いかにユーザーの離脱を防ぎ、成果につなげるか」がデザインの価値を左右します。FigmaやAdobe XDなどのプロトタイピングツールを活用し、ユーザー視点に立った情報設計やインタラクション設計ができるWebデザイナーは、今後も重宝されるでしょう。
また、UI/UXの基本概念を理解しておくことで、ディレクターやマーケター、エンジニアとの連携もスムーズになり、プロジェクト全体における貢献度も高まります。
マーケティングやビジネス視点の理解
現代のWebデザイナーには、「売れる」「問い合わせが増える」といった成果に直結するデザインが求められます。そのためには、単にデザインスキルだけでなく、マーケティングやビジネス視点の理解が不可欠です。
たとえば以下のような知識は、特にフリーランスや事業会社で働くWebデザイナーにとって大きな武器になります:
- ターゲット設定(ペルソナ設計)
- コンバージョン率(CVR)の改善施策
- SEOや広告との連携を考慮した構成
- ヒートマップやアクセス解析データの活用
これらを踏まえた提案ができるWebデザイナーは、単なる「作業者」ではなく、「パートナー」としてクライアントから信頼され、継続的な依頼にもつながります。
コミュニケーション能力とチームワーク
意外に見落とされがちですが、コミュニケーション能力やチームでの連携力も、今後のWebデザイナーにとって極めて重要なスキルです。Web制作は一人で完結する仕事ではなく、ディレクター、エンジニア、マーケターなどさまざまな職種と連携しながら進めていく必要があります。
特に近年は、リモートワークの増加やツールを使った非対面のやり取りが主流になり、適切な情報共有・要件のすり合わせ・フィードバックの受け入れと反映など、対話力が求められるシーンが増えました。
また、クライアントと直接やり取りするフリーランスであれば、ヒアリング力や提案力も重要です。「話しやすい」「意図を汲んでくれる」「フィードバックへの対応が早い」といった印象は、スキルそのものと同じくらい評価される要素になります。
将来性のあるWebデザイナーになるための方法
「Webデザイナーはなくなる」といった不安がある中でも、変化に対応し、今後も選ばれるWebデザイナーになるための道は確実に存在します。重要なのは、時代の流れを見据えて「価値を生み出す側」に立つことです。
ここでは、将来性のあるWebデザイナーとしてキャリアを築くために、今すぐ実践できる4つの方法をご紹介します。
プラスαのスキルを身に付ける
Webデザインの基礎スキルだけでは、今後ますます厳しくなる市場で埋もれてしまう可能性があります。そこで重要なのが、「+αのスキル」を掛け合わせることです。
たとえば、
- コーディングスキル(HTML/CSS/JavaScript)
- CMSの理解(WordPress、Shopifyなど)
- Webマーケティングの基礎知識(SEO、広告、CVR最適化)
- ライティングスキル(コンテンツ設計やUIテキスト作成)
など、周辺スキルを習得することで、提案力・対応範囲が広がり、クライアントからの信頼も高まります。「一人で幅広く対応できる人材」は、企業・個人問わず引く手あまたです。
知識と経験をかけ合わせて独自の強みを持つ
将来性を確保するためには、「○○ならこの人」と言われるような独自の強みや専門性を持つことが大きな武器になります。
以下は一例です。
- BtoBに特化したコーポレートサイト設計が得意
- 美容・健康業界のLPデザインに強い
- ノーコードツール×デザインの両方ができる
- 海外向けWebサイトの構築経験が豊富
このように、特定の分野やニーズに強みを持つことで、価格競争に巻き込まれにくくなり、リピートや紹介の可能性も高まります。
経験値を重ねる中で、自分の得意分野やスタイルを見つけ、それを発信・明文化していくことで、唯一無二のWebデザイナー像が築かれていきます。
SNSを活用したセルフブランディング
個人の発信力がキャリアを左右する時代。SNSやポートフォリオサイトを活用したセルフブランディングも、将来性を高めるための重要な手段です。
- 制作実績の発信(Before→Afterの比較など)
- デザインの考え方や制作プロセスの共有
- スキルの習得過程をリアルタイムで発信
- フォロワーとの交流や案件の獲得
特にInstagramやX(旧Twitter)、noteなどは、Webデザインとの相性も良く、うまく活用すれば「自分のブランド」を築いて信頼を獲得し、直接仕事を受けることも可能です。
また、自分の発信が誰かの参考になったり、応援されたりすることで、モチベーションの維持や人脈形成にもつながります。
最新情報・トレンドの収集と継続的な学習
Web業界は日進月歩。ツール、トレンド、ユーザーの動きなどは常に変化しており、それに対応できるかどうかが将来性を大きく左右します。
たとえば、
- デザインのトレンド(ミニマル、グラデーション、ネオモーフィズムなど)
- 新しい制作ツールやAI機能
- ユーザー行動の変化やSNSのアルゴリズム
- Googleの検索アップデートやSEOトレンド
これらを定期的にキャッチアップし、自分のアウトプットに反映させることで、常に「今の時代に合ったWebデザイン」が提供できるようになります。
具体的には、以下のような方法での学習が効果的です。
- 海外・国内のデザインギャラリーを見る
- 有名デザイナーや企業のSNSをチェック
- UdemyやYouTubeでスキルアップ
- 毎月1本の新しいWebサイトを模写・分析する
学び続ける姿勢こそが、Webデザイナーとして生き残るための最大の武器になります。
Webデザイナーのキャリアパスと将来設計

Webデザイナーとしてのキャリアは、多様な進み方が可能です。スキルや興味、ライフスタイルに合わせて、自分に合った将来設計を描くことが大切です。ここでは代表的なキャリアパスと、それぞれの特徴・ポイントを解説します。
スペシャリストとしての専門性を高める
一つ目は、デザインの専門性を深めてスペシャリストとして活躍する道です。UI/UXデザイン、モーショングラフィックス、アクセシビリティ設計など、特定分野に特化して高度なスキルを磨くことで、市場価値を高められます。
この道のメリットは、専門領域における第一人者や業界内での高い評価を得やすいこと。大手企業や専門的な案件での需要が安定しているため、安定した収入やポジションを目指せます。
ただし、技術やトレンドの変化に敏感に対応し続ける必要があり、継続的な学習は欠かせません。
マネジメント職へのキャリアアップ
次に、チームリーダーやプロジェクトマネージャーなど、マネジメント職を目指すキャリアも人気です。デザインスキルだけでなく、プロジェクト管理やメンバー育成、クライアント対応など幅広い能力が求められます。
マネジメント職の魅力は、組織の中での影響力が大きくなること。また、給与面でも専門職より高くなる傾向があります。複数の案件や部署を横断して調整を行うため、コミュニケーション力や調整力も磨かれます。
一方で、現場でのデザイン作業からは距離を置くことが多くなるため、「手を動かし続けたい」という人には向かない場合もあります。
フリーランスや起業による独立
最後に、自分の裁量で働きたい人に向けたフリーランスや起業による独立という選択肢があります。自由な働き方やクライアント選び、収入の上限を自分で決められるメリットがあります。
独立するには、営業力やセルフブランディング、税務や契約の知識も必要です。また、収入が不安定になるリスクも伴うため、計画的に準備を進めることが重要です。
成功すれば、大きなやりがいと収入アップを実現できる一方、自己管理能力と柔軟な対応力が求められます。
Webデザイナーの未来は自分次第
Webデザイナーの仕事が「なくなる」と断言されるわけではありませんが、今後も安定して活躍し続けるためには、スキルアップやキャリアアップを常に意識することが欠かせません。技術やトレンドは日々進化しているため、学び続ける姿勢が何よりも重要です。
また、将来の方向性に悩んだり、どうキャリアを築くべきか迷う場合は、一人で抱え込まずに転職エージェントなどの専門サービスを活用するのも有効な手段です。プロのサポートを受けることで、自分に合った選択肢や可能性が広がります。
変化の激しいWeb業界だからこそ、自分自身の成長と柔軟なキャリア設計を大切にし、前向きに未来を切り拓いていきましょう。