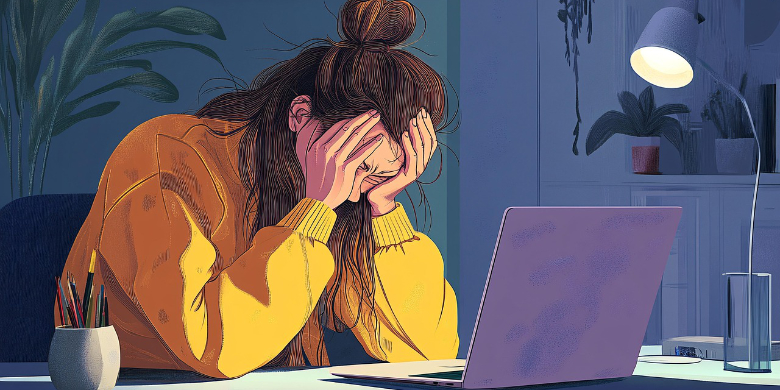テレビドキュメンタリー『情熱大陸』では俳優や作家をはじめとした著名人の仕事や私生活に迫り、一方映画『園子温という生きもの』では鬼才園子温のアトリエや制作現場に潜り込む。
また、日本未公開作品『ラーメンヘッズ』ではラーメン界の絶対王者の異名をとる「中華蕎麦 とみ田」の店主・富田治に1年以上にわたり長期密着等々、注目の人物を追いかけ続けるドキュメンタリー制作会社、株式会社ネツゲン。
今回は代表取締役の大島新さんにインタビュー。大島さんのご経歴から見る映像業界、そして、ドキュメンタリーにおけるクリエイティビティについてお話しいただきました。
「ドキュメンタリー制作に関わり続けたい」― その思いでネツゲンを設立。
 子供の頃に伝記が好きだったということも影響しているかもしれないですね。また、若いころは活字のノンフィクションが好きで、その中でも特にノンフィクション作家・沢木耕太郎さんの作品が好きでした。大学を卒業後は1995年にフジテレビに入社し、ドキュメンタリー番組を主に制作する企画制作部に配属されました。入社当時、企画制作部が担当していた人気番組は『ワーズワースの冒険』(94-97年)でした。
子供の頃に伝記が好きだったということも影響しているかもしれないですね。また、若いころは活字のノンフィクションが好きで、その中でも特にノンフィクション作家・沢木耕太郎さんの作品が好きでした。大学を卒業後は1995年にフジテレビに入社し、ドキュメンタリー番組を主に制作する企画制作部に配属されました。入社当時、企画制作部が担当していた人気番組は『ワーズワースの冒険』(94-97年)でした。
あわせて読みたい
入社のきっかけは、ちょうど僕が学生の頃にフジテレビの『NONFIX』(89年-現在)という深夜のドキュメンタリーが始まって、当時は無名でしたけれども、後に映画監督になる是枝裕和さんや森達也さんが作家性の強いテレビドキュメンタリーをつくっていて「面白そうだな」と思ったからです。
入社当初の状況はと言いますと、今もやっている『ザ・ノンフィクション』(95年-現在)が始まりました。僕は『ムツゴロウとゆかいな仲間たち』(80-2001年)という北海道の動物番組に配属されまして、そこでADをやりました。そして、同じ時期に『グレートジャーニー』という探検家・関野吉晴さんが世界中を旅する番組が始まり、その番組でも3年間ADをやりました。AD業務と並行して『ザ・ノンフィクション』と『NONFIX』のディレクターをやりました。
そして入社4年半くらい経った99年の8月に退職したんですね。退職の理由は民間放送の場合、テレビ局員がディレクターとしてドキュメンタリー番組を作る機会がきわめて少ないということが分かったからです。若いころに皆、思い出づくりのように1・2本はやるんですけれども、段々そういう機会はなくなっていくんですよね。
さらに、ドキュメンタリーの番組枠は少ないですし、その上、番組を作っているのがほぼ制作会社という状況でしたから。当時は1500人に1人しかいない『ザ・ノンフィクション』のプロデューサーになるとかでしかドキュメンタリーに日々関わっていくことはできなかったんです。でも若いうちにプロデューサーになったとしても、現場に行けるわけではありません。僕は自分で取材をするディレクターをやりたかったんです。
しばらくフリーでドキュメンタリーを中心にやってはいたのですが、それだけだと経済的に厳しく、バラエティーとか色々な仕事を掛け持ちしながらやっていましたね。またフリーだと放送局と直接契約することが難しく、「それなら自分で会社を持っている方が仕事の幅も広がるかな」と思って2009年にネツゲンを設立しました。
ドキュメンタリーにおけるクリエイティビティとは?
事実というものがあって、それを自分で取材して表現するのがドキュメンタリーなんですが、やっぱり作り手の解釈というものが大きいんですよね。解釈の部分で作品とか番組が変わってくる。そこが一番面白いかな、という気がします。それが著名人であろうが一般の人であろうが、ある事件を取り扱ったドキュメンタリーだろうが、取材者や作り手の解釈や意図が作品へ確実に出るんですよね。「他の誰でもない私が見たこの人はこういう人なんだよ」ということを伝えられるんです。
そもそもカメラが入った時点である意味異常な空間というか、その時点で意図が入っています。そして、その人の何を撮るか、どういう質問をするか、を考えて映像化していく中にもクリエイティブな作業があります。ドラマやシナリオのあるものとは違うので編集における選択の幅は広いですよね。
今のドキュメンタリーは機材がどんどんよくなっているので、何百時間も撮ることができます。それを60分の番組なら60分に収めていくというのは、ものすごく意図的な作業で、クリエイティビティという意味では「どう編集で切り取るか、構成するか」になりますかね。例えば『園子温という生きもの』がそうでしたけれども、あれは凄く時間をかけました。最初の編集である第一稿の時と、最終の映画館で見て頂いたものはまるで違う作品だと思います。
これからの映像表現の場は「国内」「テレビ」だけに留まらない
『二郎は鮨の夢をみる』(11)というアメリカ人の若い監督が撮ったドキュメンタリー映画があって、凄く良かったんです。でも、一方でちょっとした違和感というか、日本人が作ったら絶対こうならないよな、というところもあって。そこで「日本の優れた文化を外国人が表現するんじゃなくて、日本人がちゃんと世界に向けて表現するのはどうだろう」「たくさんある日本の文化の中で作品の主題として面白いのはなんだろう」と考えました。そして、「これはもう絶対ラーメンだ!」と思ったんですね。それでリサーチをしながら、『情熱大陸』等で食の職人を数多く撮られてきた、僕の先輩にあたる重乃康紀さんに監督をお願いし、ラーメンの映画を作ることにしました。

今、日本一のラーメン屋と言われる「中華蕎麦 とみ田」の店主・富田治さんに長期取材をした、『ラーメンヘッズ』(17、日本未公開)について海外のエージェントとの契約交渉を始めているんですけれども、NetflixやAmazonプライムのようなネット配信サービスへどう売っていくか、というような話が劇場配給の話より先にくるというようなことを海外担当から聞いています。
だから、30代のスタッフには、「僕はこのまま映画とかテレビで逃げ切れるかもしれないけれども、君たちはそうはいかないから、自分たちの表現の出し先を考えておいた方が良いよ」と話していますね。日本の視聴環境は人口減という問題やネット配信の発達があって、テレビにおいては少しずつ国内の業界がしぼんでくることは間違いないじゃないですか。
あわせて読みたい
だから、海外でも売れる作品じゃないとなかなか未来は厳しいのかなと思います。うちも経営していくためには既存のテレビ番組も続けていきますが、何らかの著作権をもった、自分の会社のオリジナルの作品をもって、それを海外で放映したり、国内でもテレビという媒体だけではなくて映画やネットで視聴者に届けるようなかたちにしないとどう考えても厳しいなと思っています。
答えのないことに向かって進む粘り強さがクリエイターには必要
企画を立てるためのアンテナはもちろん大事だと思いますが、やっぱり作品をつくっていくことは大変なので、そこに耐えられる粘り強さが必要です。トラブルもあるし、被写体と必ずしも良好な関係を続けられるとも限らないですし。また、編集したあとにプロデューサーからチェックを受けて、意気消沈してしまう人もいます。何でこのようなことが起こるのかというと「答えがないことに向かって進んで行って、答えらしきものを最後に出さなきゃいけない」からなんですよね。

だけど、その答えのないことにああでもないこうでもないという話をずっと続けていかなくちゃいけないのがドキュメンタリー制作なんです。そしてやっぱり、作品が出来たときに「面白かった」とか、ちょっと大げさかもしれないけれど、「社会に対して意義があった」とか、そういうことを思えれば、続けられると思います。これを踏まえて、愉快で真面目な人、ちゃんと人付き合いができて相手のことをちゃんと思いやりれる人と一緒に仕事がしたいですね。特別な映像の才能は必要ないです。被写体との対話が最も大切ですから。
(取材・ライティング・編集・撮影:CREATIVE VILLAGE編集部)