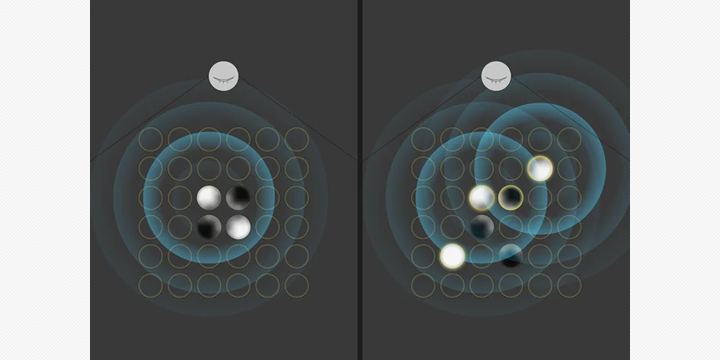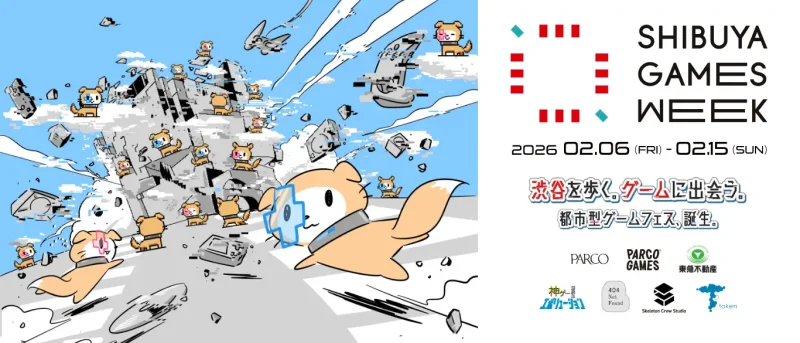世界的なストックフォト企業「ゲッティイメージズ」は、障害のある人々の広告やメディア表現に関する最新調査結果を発表した。日本では11月15日にデフリンピックが初開催されるが、障害のある人々を日常的な存在として描くビジュアルの少なさが課題として浮き彫りになっている。
調査を行ったのは、ゲッティイメージズが市場調査会社MarketCastと連携して実施する「VisualGPS」リサーチ。26か国の消費者と専門家1万人を対象とし、世界規模で求められているビジュアルトレンドを分析した。その結果、広告やブランドビジュアルにおいて障害者が登場する割合は全体の1%未満にとどまっていた。
回答者の約7割が「障害者をメディアで平等に表現してほしい」と答え、8割超が「障害のある人にも平等な機会を」とする一方で、実際の広告では車いすや義足など目に見える障害に限られる傾向が強いことも明らかになった。聴覚や精神面など、いわゆる「見えない障害」はほとんど視覚化されていない。
ゲッティイメージズは、特にデフリンピックなど聴覚障害者の活躍が注目される機会に合わせ、企業やブランドに対して多様かつリアルな表現を求めている。調査では60%の日本人が「障害者が日常の場面に登場するビジュアルに注目している」と回答し、68%が「多様な特性のある人々が広告に登場することで相互理解が進む」とした。
現在、日本の広告で多く見られる障害者の表現は「希望」「支え」「痛み」といったテーマに集中している。希望を象徴するイメージとしては、自然の中で他者に車いすを押される光景が多く、サポートを示す場面では手をつなぐシーンや介助の映像が使われている。これらの表現は温かさを感じさせる一方、障害者が「支援される存在」として描かれがちだ。
調査チームは、リハビリや治療の場面に偏らず、日常の喜びや趣味、家族との関わりを描くことが重要だと指摘する。また、若い世代のファッションやデジタル文化に親しむ姿、働く姿を取り上げることで、「特別ではない日常の多様性」を示すことができるという。
ビジュアルが人々の認識を形づくる影響は大きい。現実の社会には、さまざまな能力を持ちながら生活する人々が存在する。その多様さを自然に伝える表現こそ、共感を呼び、ブランドの信頼を高める力を持つとゲッティイメージズは提言している。